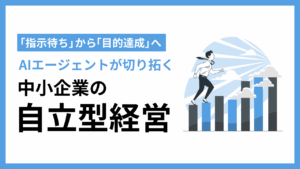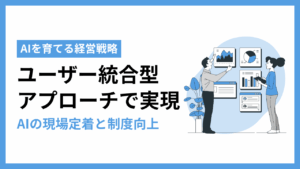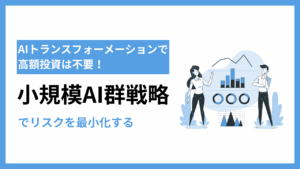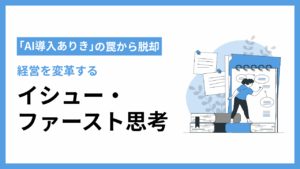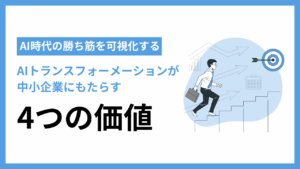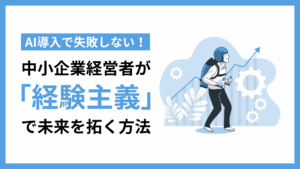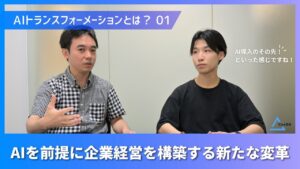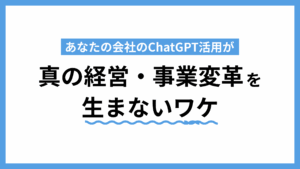【完全解説】CosBE流AIトランスフォーメーション4つの導入ステップ
「小さく始めて大きく育てる」CosBE流の「AIトランスフォーメーション」とは?
「AIを導入したけど、結局何も変わらなかった…」
そんな経営者の悩みを解決するため、今回はAIトランスフォーメーションを成功に導く4つの必須条件と、CosBEが実践する失敗リスクを最小化する導入手法について、代表の茂見さんに詳しく伺いました。
重要なのは、AIありきで始めるのではなく、経営課題から逆算してAI活用を検討すること。そして完璧な計画よりも、小規模な実証から始めて段階的に拡張していくアプローチです。
この手法により、多くの企業が「生産性改善」から始まり、最終的に「新たな顧客価値創造」まで発展させています。
この記事のインタビュアー
小渕 茉那虎(こぶち・まなと)/株式会社NEW PHASE 代表取締役
動画制作・Web制作を中心に中小企業向けのクリエイティブ支援を展開。都内での経営者交流会も主催しており、経営現場の声に日々触れている。
現在はCosBEの営業顧問として、AIに関心を持つ経営者の声を汲み取り、現場視点での情報発信やインタビューを担当。
AIトランスフォーメーション成功の4つの必須条件
多くの企業がAI導入で失敗する理由としては、技術的な問題だけでなく、根本的なアプローチの問題もあげられます。
CosBEが実践する成功の4つの前提条件を詳しく解説します。
イシューファースト 経営課題から始める革新的思考
小渕: AIトランスフォーメーションを成功させるために、まず何から始めるべきでしょうか?
茂見さん: 進め方について話していくにあたって、その前提として大事な考え方が4つあります。まず1つ目の**「イシューファースト」**という考えですが、AIトランスフォーメーションの議論をしていますけども、一旦AIを使うことを目的とするのではなくて、AIから離れてますね。
自分の会社がどこを目指すのか、何が大事な課題なのか、こういったことから入っていく課題を明確にしていきながら、そこに対してAI技術を使った構想に仕上げていく。この目的を経営目標だったり経営課題の解決というところに置く、これがイシューファーストという考え方です。
小渕:AIを使うこと自体が目的ではないということですね。
茂見さん: その通りです。まずは経営課題を明確にし、それを解決するための手段としてAIを検討します。最終的にAIを使わない結論になる場合もありますが、それで構いません。重要なのは「何を解決したいのか」を明確にすることです。何に取り組むかによってアプローチが変わりますし、目的が解決できれば場合によっては最終的にAIを使わなくても良いわけです。
リーン&アジャイル 小さく始めて大きく育てる実践法
小渕: 開発するのがゴールではなく、その前に経営課題の棚卸しが必要ということですね。
茂見さん: 2つ目が「リーン&アジャイル」といった考え方です。これは「リーンスタートアップ」といった考え方と開発手法であるアジャイル開発といったことを組み合わせた考え方。最初に計画をしっかり立てて計画通り進めるという考え方ではなくて、小さなものからまず実際に始めて、実際にその使ってみた結果、始めてみた結果を踏まえて次のステップに進んでいく。
こういう小さく始めて育てていくようなアプローチがリーンとアジャイルです。使ってみた結果を踏まえて次のステップに進むことで、見えていなかった課題や暗黙知が明らかになります。事業の大事なところは細部に宿っていて、それは最初に現れてこないんです。
小渕: 最初から完璧を目指すのではなく、改善を重ねながら進化させていくということですね。
茂見さん: そうです。やってると分かるんですけども、事業の大事なところっていうのは、細部に宿っている。で、細部に宿っているところはクライアントさんも言語化できてない、可視化できてないんです。客観的な視点を経験値として持っている会社の強みや工夫といったものが、事業の中に最初からあります。
こういったものは最初に現れてこない。ただ細かい課題を設定してそこに向けて最初に小さく始めてみると、その始めてみた過程の中で今まで可視化されてこなかった暗黙知が出てくる。これが非常に重要で、ここが見えてくるからこそ最初は小さく始めましょうということなんです。
小規模AI群 用途特化型で精度と柔軟性を両立
小渕: 始めてみないと分からない経営課題が顕在化してくるということですね。実際のAI開発においては、どのような規模感で始めるのが効果的なのでしょうか?
茂見さん:3つ目が「小規模AI群」という考え方です。これは万能なAIを1つ作るのではなく、絞り込んだ用途に特化した小さなAIを複数作って、それを連携させて活用していくという考え方です。技術的には、情報の対象を狭めた方がAIの精度は上がります。なので、精度の高いAIを早く使いたいなら、小さく作ってたくさん用意する方が合理的なんです。
小渕: 実際に運用する際のメリットもあるのでしょうか?
茂見さん: はい。AI同士を連携させて業務を分担させれば、柔軟性が高くなります。また、1つの巨大なシステムに比べて、更新や改善も部分的にできるので、時間もコストも節約できます。大規模システムは導入・改修に多くのコストと時間を要しますが、対して小規模AIは、環境変化に素早く対応でき、必要に応じてアップデートも容易です。AI技術の進化が早い今、俊敏さは大きな武器になります。
小渕: なるほど。一つひとつは小さくても、連携することで大きな効果を生み出すということですね。
茂見さん: その通りです。そして何より重要なのは、解決したい課題を定める時にこれをとにかく細分化してブレイクダウンして解決可能な最小単位のところの目的を設定することです。この最小単位での実証が成功の鍵となります。
ユーザー統合型アプローチ 人とAIが協働で成長する仕組み
小渕: AIと人の役割分担も重要になってくるということでしょうか?
茂見さん: 4つ目が「ユーザー統合型アプローチ」です。これは、データが整っていないからAI導入を諦めるのではなく、ユーザーと一緒に使いながらAIを育てていく考え方です。全てを一気にAIで置き換えるのではなくて、一部はユーザーが引き続き指示をしたり評価をしたりといったことを組み合わせます。
たとえば、AIの出力精度が低ければ、ユーザーが少し教えてあげたり補正を加えたりすることで、実務を回せるようになります。そしてそのやりとりが新たなデータとなって蓄積され、AIが成長していくんです。これを再度AIに学習させながらより高みを目指していく、こんなアプローチですね。人の感性でしか判断できないところに人が集中することで、AIと人が最適に協働できるんです。
小渕: まさに、AIを育てるという感覚ですね。新入社員を育成するようなイメージに近いかもしれませんね。
茂見さん: その通りですね。初めはできることが少なくても、使いながらどんどん賢くなる。だからこそ、すぐに導入を始めることができます。「データがないからAIは無理」と考えるのではなく、「使いながらデータを蓄積する」という柔軟な発想が重要です。ユーザーが能動的に関わることで、より実務に即したAIシステムへと成長していきます。
- イシューファースト:AI導入は課題解決が目的であり、AI活用は手段
- リーン&アジャイル:小さく始めて改善を重ね、暗黙知を顕在化
- 小規模AI群:用途特化の小型AIを多数作り、連携で柔軟性を実現
- ユーザー統合型:人とAI協働で使いながらAIを育成し、データ不足を解決
 茂見氏
茂見氏この4つの必須条件は、いずれも「失敗リスクを最小化しながら素早く価値を生み出す」ことを目的としています。
特に小規模AI群とユーザー統合型アプローチは、AI技術の特性を活かしながら企業の既存資産(人材・ノウハウ)を最大限に活用する手法です。
小規模な実証を通じて企業固有の暗黙知を発見し、それをAIと人の協働で価値創造につなげることで、他社では真似できない独自の競争優位を構築できます。
CosBE流 失敗しないAI導入の4ステップ
CosBEが実践するAIトランスフォーメーションは、経験主義に基づいた段階的アプローチです。計画重視のPDCAサイクルではなく、変化を前提とした進化型プロセスが特徴です。
ステップ1-2 課題明確化から構想策定まで
小渕: 実際にCosBEさんがAIトランスフォーメーションを進める具体的な手順を教えてください。
茂見さん: 我々のトランスフォーメーションの進め方は経験主義に基づいた進め方です。最初にやるべきことはイシューファーストといった考え方をお話しましたけども、課題を明確にすることですね。今会社がどのような状態で将来どこを目指していてそのためには何が大事なのか、こういった経営者としての大きなビジョンであったり課題感、まずここから入っていきます。
ここから入っていった時にその目標達成あるいは課題を解決するためにどういうAIを使ったソリューションが考えられるか。これがAIソリューションの構想になる。ですので目的から入って次にやるものは構想を描くこと。ただこのタイミングのAIの構想は非常にラフなもので構いません。ぼやっとしたものでも全然構わないですね。
小渕: 経営課題の整理が最初の重要なステップということですね。
茂見さん: はい。どれだけこの課題を明確にできるかっていうところが1つ大事で、やっぱり相談の中でも最初に何に取り組むかみたいなことを真剣に悩んでいらっしゃる会社さんもいらっしゃいますけども、何に取り組むかで結果が変わってくるんで。この段階での経営者との対話は非常に重要です。
ステップ3-4 MVP開発から事業変革まで
小渕: 小さくミニマムで始めたらある程度の課題感が出てくるし、ビジョンも湧いてくる。そこに対してどんどん肉付けをしていく感じですね。
茂見さん: この構想を立てた時にこの中で一番最初の第一歩として何をするか、これを絞り込む。この絞り込んだものを我々MVP(Minimum Viable Product)っていう風に呼んでるんですけども、この構想の第一歩を絞りに絞り込んだ最小単位のものをどう定義するかって、これを定義したらまずこれだけに集中して実際に絞り込んだ課題を解決することをやってみます。これがMVP開発を通してやっていくと。
進めていきますと、実際に一つの経営課題をAI技術を使って解決したという経験値が溜まりますし、解決のためにまた色んなより細かいものが見えてきます。その経験を踏まえて最初に立てた構想をより具体化することができるんです。
小渕: 実践を通じて、当初見えていなかった課題や機会が明らかになってくるということですね。
茂見さん: そうです。最初の第一歩を進められたらこれら3つができるんです。構想を具体化できる、プロダクトを進化させる、それから実際に浸透させていく。この3つをこの先並行させていく。そしてどんどんどんどん良いものにしていって大きな構想を実現していく。こういったプロセスで最終的には企業の変革まで至る。こういう進め方ですね。
| ステップ | 目的 | 具体内容 | 期待される成果 |
|---|---|---|---|
| ステップ1 課題明確化 | 経営ビジョンと課題の 特定 | 現状分析、将来目標設定、重要課題の抽出 | 解決すべき本質的課題の明確化 |
| ステップ2 構想策定 | AIソリューションの 大枠設計 | 課題解決に向けたAI活用案の検討(ラフでOK) | 実現可能性のある解決方針の策定 |
| ステップ3 MVP開発 | 最小単位での 実証 | 課題を細分化し最小限の機能で解決案を実装 | 実用性検証と暗黙知の顕在化 |
| ステップ4 改善・拡張 | 段階的スケールアップ | 構想具体化・プロダクト進化・現場浸透を並行実施 | 持続的改善と事業変革の実現 |
MVPで2カ月でAIサービスを実現!CosBE支援のS社成功事例
本記事でご紹介した「小さく始めて大きく育てる」MVPアプローチを実際に実践し、わずか2カ月でAIサービスのプロトタイプを完成させた企業事例をご紹介しています。
S社は「要件が固まらない」「開発に時間がかかりすぎる」という典型的な課題を抱えていましたが、完璧な仕様を求めず「まず動くもの」を最優先で開発することで見事に解決。RAG×LLM技術を活用した具体的な進め方と成果をぜひご覧ください。
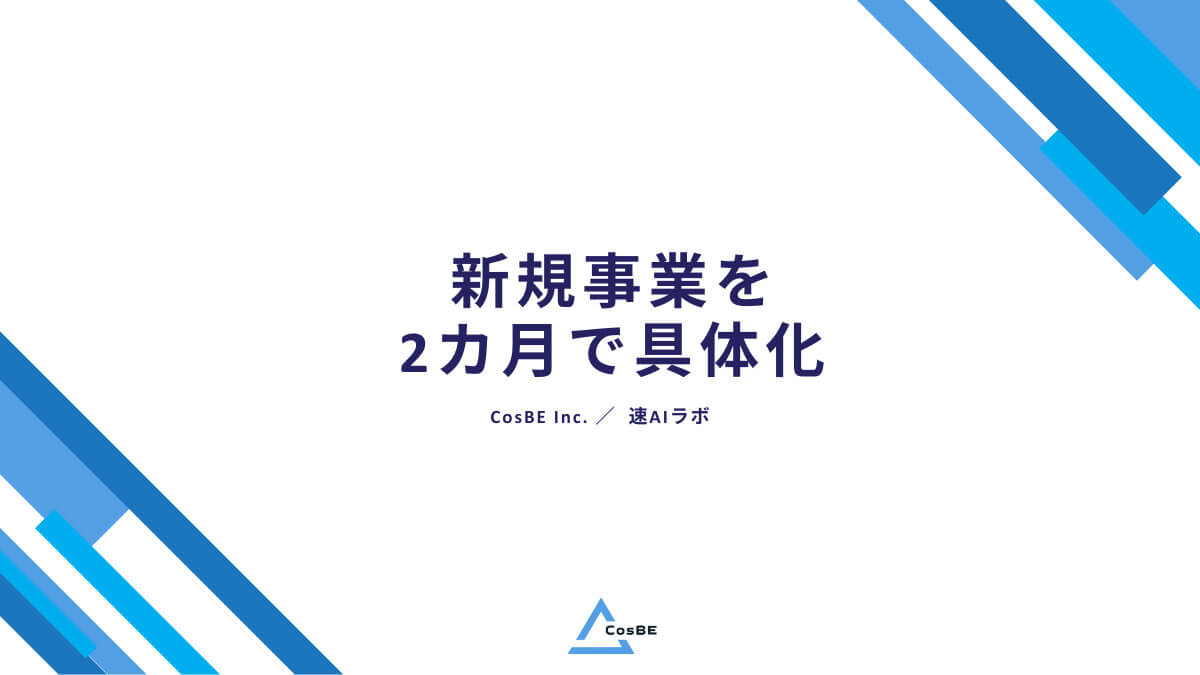
- 経営課題→構想→MVP→改善・拡張の順で進める
- 初期構想は柔軟でOK、実践を通じて具体化
- PDCAではなく、変化前提の進化型サイクル
 茂見氏
茂見氏MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)は、リスクを最小限に抑えながら市場や社内での実用性を検証する手法です。
AIトランスフォーメーションにおいては、完璧なシステム構築を目指すのではなく、最小限の機能で実際の業務課題を解決することから始めます。
この過程で企業固有の業務フローや暗黙知が明らかになり、より効果的なAI活用の方向性が見えてきます。
実践成功事例 生産性改善が価値創造に発展
実際のCosBEクライアント事例を通じて、AIトランスフォーメーションがどのように企業の成長エンジンとなるかを具体的に解説します。
課題設定 人手不足による業務停滞の解決
小渕: 構想は最初に立てるけれど、やっていくと変わっていくということですか?
茂見さん: 変わっていくし変えた方が良いんです。なぜかというとやったことによって新しいことがどんどん分かるので、新しく分かったことをもとに将来を描いていきます。
我々のお客様を例で言うと、最初に取り組んだことは生産性の改善っていうことだったんですね。人が足りなくて仕事を受けきれないという時に、まずは人でやっているところの時間かかっているところをAI技術で解決するということを絞り込んでやってます。
小渕: 人手不足という現実的な課題から始まったということですね。
茂見さん: そうです。これが実は非常に重要で、具体的で切実な課題から始めることで、AI導入の必要性と効果が明確になります。抽象的な「DXを進めたい」ではなく、「この業務で1日2時間かかっている作業を短縮したい」といった具体的なレベルまで落とし込むことが成功の鍵です。
成果拡大 新たな顧客価値の創出へ
小渕: 改善するというよりは解決して次のステップに進んでいる感じですかね。
茂見さん: そうすると今まで実際にやってた業務をAIにある程度任せて、人は人の感性でしか判断できないところに集中するんです。そうすると今度は生産性の改善だけではなくて、納期が短縮されるだとか、アウトプットの質が上がるといった成果が出始めます。
そうすると何に気づき始めるかというと、これAIを使ってただ単に仕事を楽にするだけじゃなくて、これがお客様に対する価値になるぞということが生まれてくるわけなんです。
小渕: 内部効率化が外部価値創造に発展していくということですね。
茂見さん: まさにそうです。今度それを、お客様の価値に変えていきながら、じゃあまた違うところにAIの技術を使って課題を解決する。こういうのをやっていくと次第に人をどうやって採用してどうやって育ててということが課題だったところが、この制約からは解放されて逆にどこに人を集中してどうやって価値を生んでいったらよりお客様に価値を届けられるかみたいな。
考え方とかビジネスのあり方もどんどん変わっていった方が良い。これがAIトランスフォーメーションの本質的な価値です。単なる効率化を超えて、ビジネスモデル自体の進化を促します。
- 具体的で切実な課題「人手不足による業務停滞」から開始
- 内部効率化から外部価値創造への自然な発展
- コスト削減思考からビジネスモデル進化への転換
 茂見氏
茂見氏この事例は、AIトランスフォーメーションの典型的な成功パターンを示しています。
当初は「コスト削減」を目的とした生産性改善からスタートしましたが、AI活用により人的リソースの最適配分が実現され、結果として顧客への新たな価値提供が可能になりました。
これは単なる効率化を超えて、ビジネスモデル自体の進化を促す事例として注目されます。
経営者が選ぶべき道 小さく始める勇気
AIトランスフォーメーションは、もはや「やるかやらないか」ではなく「いつから始めるか」の問題です。CosBE流アプローチが示す成功への道筋を解説します。
リスク最小化と段階的スケールアップ
小渕: このCosBEさんのAIトランスフォーメーションの進め方を聞くと、ミニマムから始めて社長目線でのコンサル領域から入ってくるというところがすごい強みだと思いました。
茂見さん: それが失敗リスクを抑えて確実に早く前に進む方法だと思います。いきなり大規模な計画を詳細に立てて進めていこうとしても、特に精度の面など不確定なところがあることも多く、いきなり大きな投資を決めてスタートを切るのがむつかしいと悩まれてる方が多かったんですが、この(リーン&アジャイルの)進め方だとやりやすいと思います。
小渕: 経営者の心理的なハードルを下げることも重要な要素ですね。
茂見さん: そうですね。多くの経営者が「AI導入は大規模投資が必要」「失敗したらどうしよう」という不安を抱えています。しかし、小規模から始めることで、実際の効果を体感しながら段階的にスケールアップできるんです。これにより、投資対効果を確認しながら進められるので、経営判断としても合理的です。
継続的な改善と企業変革
小渕: ツールを開発して終わりとかではなくて、構想と現場が何度も対話しながら話し合って改善していきながら次のステップに進化していくプロセスが必要ということなんですね。
茂見さん:その通りです。これって最初に計画していたわけじゃなくて、導入を進めていく中で何ができて何ができないかがより明確になっていって、それを踏まえてビジネスをもう一度考え直すという風になっていきます。
小渕: 計画通りに進めるのではなく、発見しながら進化していくということですね。
茂見さん: はい。だからこそPDCAにならないんですよ。構想は最初に立てるんですけども、やっていくとこれ変わっていくんですね。変わっていくし変えた方が良いんです。なぜかというとやったことによって新しいことがどんどん分かるので、新しく分かったことをもとに将来を描いていきます。
この継続的な対話と改善のプロセスが、プロジェクトをAI導入にとどまらせるのではなく真の企業変革へと発展させる原動力となります。
- 小規模開始でリスクを最小化し確実な前進を実現
- 継続的対話により構想と現実の最適化を図る
- 制約解放からビジネスモデル再構築への発展
 茂見氏
茂見氏CosBE流AIトランスフォーメーションの最大の特徴は、技術導入よりも「経営変革」に主眼を置いている点です。
小規模なMVPから始めることで、企業は多額の投資リスクを負うことなく、AI活用の可能性と限界を実体験できます。
この過程で得られる知見は、単なる業務効率化を超えて、企業の根幹となるビジネスモデルの再構築につながり、持続的な競争優位の源泉となります。
従来のDXとAIトランスフォーメーションの決定的違い
多くの企業が混同しているDX(デジタルトランスフォーメーション)とAIトランスフォーメーションには、根本的なアプローチの違いがあります。この違いを理解することが、成功への第一歩となります。
人主導から AI協働への転換
小渕: DXとAIトランスフォーメーションって、具体的にどこが違うんでしょうか?
茂見さん: DXは「人がデジタルツールを使って業務を改善する」というアプローチです。一方、AIトランスフォーメーションは「AIと人が協働して新しい価値を創造する」という発想なんです。つまり、AIに一部の判断や実行を委ねることで、人間はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。
小渕: 人とテクノロジーの関係性が根本的に違うということですね。
茂見さん: その通りです。DXでは人がデジタルツールを操作することが前提ですが、AIトランスフォーメーションではAIが自律的に判断・実行する部分が存在します。これにより、従来は人間が行っていた定型業務や分析業務をAIが担い、人間はより戦略的で創造的な業務に専念できるようになります。
計画型から経験型への進化
小渕: 進め方も違ってくるということですね。
茂見さん: そうです。従来のDXは計画を立ててその通り進めるPDCAサイクルでしたが、AIトランスフォーメーションでは構想が変化することを前提としています。実際にAIを使ってみることで新しい気づきや可能性が生まれ、それに合わせてビジネスモデル自体を柔軟に変えていく。これが経験主義的アプローチの本質です。
小渕: 不確実性の高いAI領域だからこそ、この柔軟なアプローチが重要ということですね。
茂見さん: はい。AI技術は日々進歩していますし、実際に使ってみないと分からない特性があります。だからこそ、変化を前提とした進化型のプロセスが必要なんです。計画に固執するのではなく、学習と適応を重視することで、より大きな成果を得ることができます。
- DXは人主導、AIトランスフォーメーションはAI協働型
- 計画重視のPDCAから経験重視の進化型サイクルへ
- 人とAIの役割分担による新しい価値創造を実現
 茂見氏
茂見氏DXとAIトランスフォーメーションの違いは、単なる技術の違いを超えて、組織運営や事業戦略の根幹に関わります。
DXが「業務のデジタル化」に主眼を置くのに対し、AIトランスフォーメーションは「人とAIの協働による新しい価値創造」を目指します。
この違いを理解することで、適切な投資判断と推進体制の構築が可能になります。
成功企業が発見する暗黙知の活用法
AIトランスフォーメーションの過程で最も重要な要素の一つが、企業に眠る暗黙知の発見と活用です。CosBE流アプローチでは、小さな実証を通じて組織の隠れた強みを可視化します。
暗黙知発見のメカニズム
小渕: 始めてみないと分からない経営課題が顕在化してくるということですが、具体的にはどんなことでしょうか?
茂見さん: 事業の大事なところっていうのは、細部に宿っています。で、細部に宿っているところはクライアントさんも言語化できてない、可視化できてないんです。客観的な視点を経験値として持っている会社の強みだったりとか工夫だったりとか、こういったものが経営の中に最初からあるんですけど、事業の中に。こういったものは最初に現れてこないです。
小渕: 企業の真の競争力が、見えないところに潜んでいるということですね。
茂見さん: その通りです。例えば、ベテラン社員が長年の経験で培った判断基準や、効率的な業務の進め方、お客様との関係構築のコツなど、こうした組織内に蓄積されているが言語化されていない知識やノウハウが暗黙知です。これらは企業の真の資産でありながら、普段は意識されることがありません。
実践を通じた組織力の再発見
小渕: それを外部の専門家の意見を聞きながら客観的な視点で発見していくということですね。
茂見さん: 細かい課題を設定してそこに向けて最初に小さく始めてみると、その始めてみた過程の中で今まで可視化されてこなかった暗黙知が出てきます。これが非常に重要で、ここが見えてくるからこそ最初は小さく始めましょうということなんです。
この暗黙知を活用することで、他社では真似できない独自の競争優位を築くことができるんです。AIトランスフォーメーションのプロセスでは、こうした暗黙知を可視化してAIに学習させることで、組織の知的資産を最大限に活用できます。
小渕: AIが単なるツールではなく、組織の知恵を増幅する存在になるということですね。
茂見さん: まさにそうです。AIと組織の暗黙知が融合することで、単なる効率化を超えた独自性のある価値創造が可能になります。これは大きな投資をして最新技術を導入しても得られない、その企業だけの強みとなります。
- 企業の真の強みは言語化されていない暗黙知に存在
- 小規模実証を通じて組織の隠れた資産を発見・可視化
- 暗黙知のAI活用で他社にない競争優位を構築
 茂見氏
茂見氏AI時代において、差別化要素はAIに学習されない独自の情報です。暗黙知はその最たるものであり、AIトランスフォーメーションにおける重要な成功要因の一つです。
多くの企業が技術的な側面に注目しがちですが、真の競争優位は組織固有の知識と経験にあります。
小規模な実証プロジェクトを通じて、これらの隠れた資産を発見し、AIと組み合わせることで、他社には模倣困難な独自の価値を創造できます。
AIトランスフォーメーションで未来を切り拓く
CosBE流AIトランスフォーメーションが多くの企業に選ばれる理由は、「小さく始めて大きく育てる」経験主義的アプローチで「失敗したらどうしよう」という経営者の不安を解消しながら確実な成果につなげるからです。
この成功の背景には、AIありきではなく経営課題から逆算して始めるという発想の転換があります。従来の「計画通りの実行」から「変化を前提とした進化」へとアプローチを変えることで、MVP(Minimum Viable Product)での素早い検証と改善を重ねながら、当初想定を遥かに超える成果を生み出しています。
実際に人手不足から始まったプロジェクトが、最終的には顧客への全く新しい価値提供へと発展した事例もあります。これは小さく始めたからこそ発見できた企業の隠れた可能性でした。
AI導入は単なる技術選定ではなく、いかに現場に根付かせ、継続的に改善していくかが鍵です。そして何より重要なのは、この過程で企業固有の暗黙知を発見し、それをAIと組み合わせることで、他社には真似できない独自の価値を創造することです。
「小さく始める勇気」さえあれば、3ヶ月後には自社でも新たな可能性が見えてくるはずです。完璧な計画を待つのではなく、今こそ最重要な経営課題を1つ選んで、小さな一歩から確実な変革への道を歩み始めてみませんか。
具体的な導入事例と成功のポイント
今回は、AIトランスフォーメーション成功のための4つの前提条件と、CosBE流の実践的導入手法について茂見さんに伺いました。
次回は、茂見さんが実際に手がけた具体的な導入事例をご紹介いただきながら、「業界別の最適なアプローチ」「よくある失敗パターンとその回避法」「ROI向上のための重要ポイント」といった、より実践的な内容をお届けする予定です。
AIトランスフォーメーションの導入を検討されている経営者の方は、ぜひ次回もご覧ください。
\AIで業務効率化を実現しませんか?/